
練習しても上手くならない、才能がないんじゃないか?
同じクラブや部活で、なぜか自分だけが取り残されている。
その辛さは、私も学生時代に経験してきました。
そして今、コーチとして指導していると、同じような相談を受けることも少なくありません。
「毎日練習しているのに勝てない」のは、努力不足だけが原因ではありません。
多くの場合、練習内容や考え方、用具の選び方などが原因になっています。
- 卓球が上達しない原因
- 本当に必要な練習と優先順位
- 練習量・用具・才能の考え方
誰でも、正しい練習方法と方向性を選べば、今より強くなることができます!
※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。リンクから商品を購入いただくと、当サイトに収益が発生する場合があります。
無駄な練習をしている
ただなんとなくやってる、言われたからやっている練習メニューだと試合では活かせず、無駄な練習になってしまします。
以下注意してみて下さい。
反省していない
試合に出たら、しっかり反省してPDCAサイクルを回して次に活かしましょう。
試合動画を撮ろう

試合に出ても動画を撮っていない人がいますが、これは致命的です。
なぜ動画が必要なのか。
試合の内容を事細かに覚えておくことは不可能だからです。
仮に覚えていたとしても、自分の主観が混じります。
試合中は平常心ではいられず、試合中の考えと実際のプレーの間には必ずギャップが生まれます。
動画があれば、自分のプレーを客観的に振り返ることができます。
初めて見たときは「思っていた以上に下手だ」とショックを受けるかもしれませんが(笑)、それこそが成長の出発点です。
最近はスマホでも簡単に試合動画が撮れる時代です。三脚も1,000〜2,000円で買えるので、常に持ち歩いて撮影できます
撮らない理由はありません。
試合内容を確認しよう
- 気持ちが落ち着いた試合の翌日以降に確認しよう
- EXCELなどで数値化して客観的に分析してみよう
- 自分がどんなことを考えながらプレーしてたか思い出そう
試合直後は、興奮していて自分のプレーに対して偏った見方をしてしまいます。家で落ち着いた状態で試合動画を確認しましょう。
派手なプレーに目が行きがちですが、地味なプレーの方が得点に影響しています。
それはただ動画を見ているだけではわからないので、試合中にどんなプレーが多かったのかを数えて、EXCELなどでまとめた上で客観的に分析をする必要があります。

優先順位をつける
試合分析ができたら、練習する技術に優先順位をつけて、やる練習とやらない練習を決めましょう。
使う頻度が高い技術を優先して鍛えることが重要です。
卓球では、サーブ→レシーブ→3球目、まででラリーの大半が終了します。
よってサーブ、レシーブ、3球目は少なくとも優先度を上げて練習をすべきです。
試合を想定していない
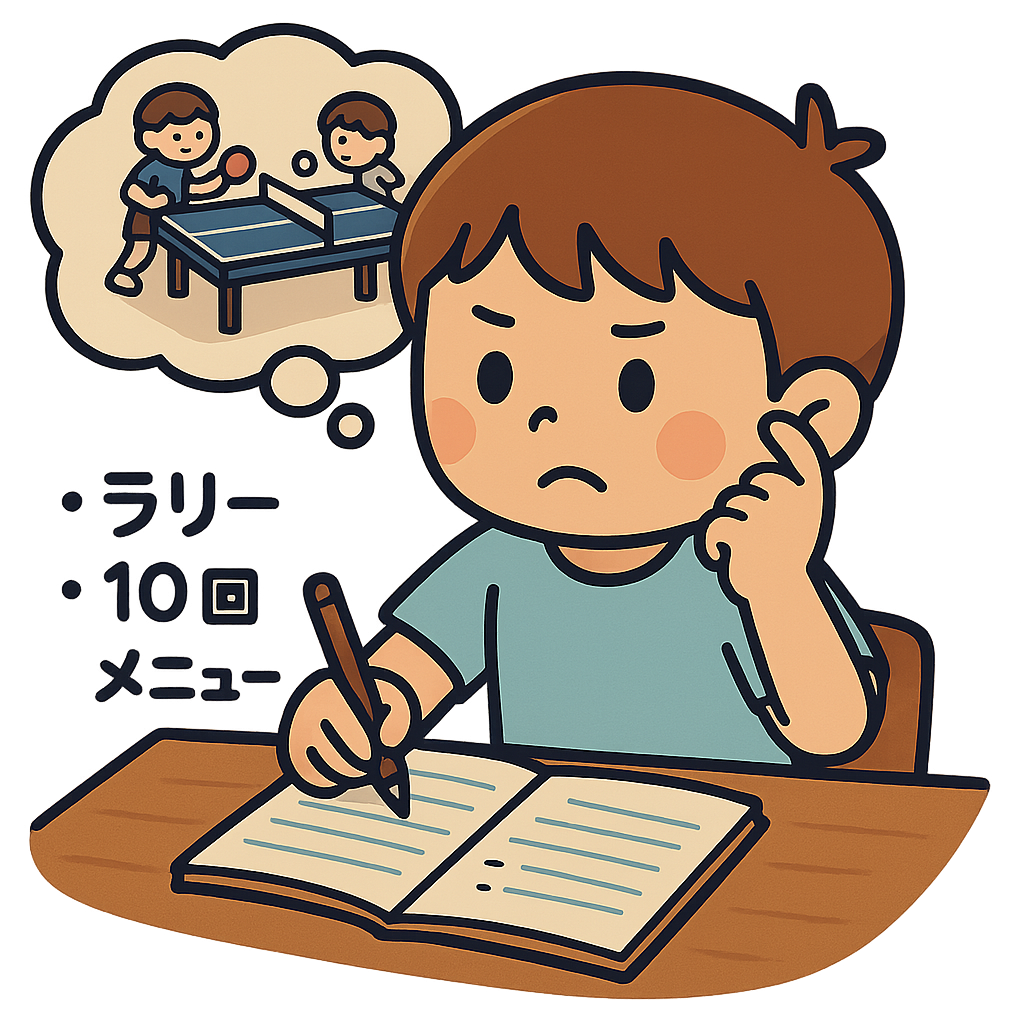
「この練習、試合のどの場面で使うのか」をリアルに想像してから練習しましょう。
ツッツキが来たらドライブを打つ!ってだけだと浅いです。
どんな場面で(ラブオール、それともデュース?)、心理状況、サーブからの展開で、使う技術なのか?
試合の場面をリアルに想像しながら練習して方が無駄な練習にならずに済みます。
ランダム性を取り入れる
実際の試合を想定すると、ある程度コースが分かっていても、逆のコースに来ても大丈夫なように対応しながらプレーをしているはずです。
練習でもランダム性を入れて練習しましょう。
例えば、ツッツキをドライブする練習では、ツッツキのコースをランダムにしたり、たまにはストップをしてもらったり、実際の試合に近い環境で、練習しましょう。
緊張感を持った練習をする

試合で力を発揮できない人は、普段の練習に“緊張感”が足りないケースが多いです。では、どうすれば緊張感を練習に取り入れられるのでしょうか。
- 誰かに見られながら練習をする
- 練習の序盤で緊張する練習をする
- 普段と違う相手・環境に飛び込む
●誰かに見られながら練習をする。
部活で練習試合をする時も、先輩などに試合を見てもらったり、誰かに応援してもらったりしましょう。誰かに見られながら試合をすると、それだけで緊張しますよね。
台数を1台にして団体戦なんかもおすすめですよ。
●練習序盤で緊張感のある練習をする
できれば体が温まる前に緊張感のある練習をしましょう。
すると、その後の練習でも、少しですが緊張感をキープしたまま練習ができます。
なんとなく普段の練習とは違って筋肉の強張りを感じながら練習できるのでおすすめです。
●普段とは違う相手・環境に飛び込む
同じ相手、同じ環境では緊張感を維持するのは難しいです。
そこで、別のチームに参加したり、普段交流のない相手と打ってみるのも有効です。知らない人に囲まれれば自然と緊張し、気を使いながらプレーすることになるでしょう。
このように、意識的に“緊張感を再現できる場”を作っておくことが、試合で実力を出すための近道です。
必要な練習をしていない
前の章では「無駄な練習」について解説しました。
では逆に、無駄になりにくい練習とは何でしょうか?
答えはシンプルです。
自分の試合を反省した上で、試合で一番使う技術を集中して練習すること。
必要な練習をしていなければ、どれだけ練習しても上手くなりません。
もちろん人によって使う技術の比重は違いますが、共通しているのは サーブとレシーブ。試合のラリーのスタートで必ず使うからです。
加えて、軽視されがちな 守備練習。
さらに、何を練習したら良いかわからない!という人に向けて、「とりあえずこれだけはやっとけ」という鉄板フットワーク練習を紹介します。
必要な練習①:サーブ練習
卓球においてサーブは最重要の技術です。
理由は2つあります。
- 必ず使う技術であること。
- サーブの種類や質によって、その後の展開が決まること。
つまり、サーブが上手ければ返ってくるボールをある程度予測できる。練習メニューもその予測をもとに具体的に立てることができます。だからこそ、サーブ練習は「すべての基盤」であり、最優先で取り組むべきなのです。
しかし現実はどうでしょう。
部活動で2時間の練習時間があったとしても、サーブ練習はせいぜい10分程度。ほとんどの人は居残り練習や自宅の卓球台がない限り、まともに取り組めていないのが実情です。
 たくぼー
たくぼーサーブ練習は一人でコソコソとやるもの!
サーブ練習のポイント
- まずは 低く短く、狙ったコースに出す
- 自分が試合で使うサーブを磨く
- 相手に出されて嫌だったサーブ、自分が試合で効いたサーブを重点的に練習する
効果が実証されているサーブを磨けば、試合本番でも確実に得点源になります。
さらに深掘りしたい人には、オリンピック金メダリストの水谷隼さんの著書『これで勝てる!サービス戦法』がおすすめ!。なんと、一冊丸ごとサービスの事しか書いてないというマニアックな本ですが、目からうろこの内容ばかり。
サーブの重要性を改めて理解できるはずです。
必要な練習②:レシーブ練習(特にツッツキ)
レシーブはサーブと同じくらい試合で頻繁に使います。その中でも最重要はツッツキ です。
理由は簡単で、ツッツキはストップ・チキータ・ドライブ・フリックなど数あるレシーブの中で唯一すべての回転・コース・長さに対応できる技術だから。
回転が読めないときでも「とりあえずツッツキ」が成立する。だからよほど実力差がない限り、一番使うレシーブになります。
ツッツキの優先順位
- まず何より返球すること!
- 低く返すこと
- コースを狙うこと
- 回転を工夫すること
2,3,4ができたら、ツッツキは十分な武器になります。
必要な練習③:守備の練習
卓球の試合の半分は自分が攻撃されている時間です。
それなのに、多くの選手は攻撃練習ばかりに偏り、守備練習を軽視しがちです。
それに中学・高校レベルでは、安定してドライブを2〜3球続けられる選手は県大会上位レベルでも少ない。
だからこそ、守備だけで勝ち上がることができます。
それに、攻撃の練習をたくさんしても、攻撃をする機会がないことはあっても、守備はやろうと思ったらできます。
なぜなら、相手が勝手に攻撃してくれるからです。
なので、ペン粒やカットマン、ブロックマンはほぼ100%自分が得意な守備の展開に持っていくことができ、有利に試合を進めることができます。
守備練習の例
- 相手ワンコース、自分オールコートでブロック練習
→ 足を細かく動かし、打ったら元に戻る - 相手サーブ → ランダムにツッツキ → 相手ドライブ → ブロックで返す
→ ツッツキの質によって返ってくるドライブが変わるので予測を意識する
こうした練習を重ねれば「ブロック1本止めるだけで得点できる」シーンが増えます。
必要な練習④:フットワーク練習


とりあえず、フットワークを鍛えておけば間違いありません。
なぜなら、フットワークは全ての技術の基本!、卓球のレベルの底上げにつながるからです。
ドライブにしろ、ブロック、ツッツキ、ロビング、全ての技術が、ボールまで正確に動くことで発動します。
例えばドライブなら、毎回同じポイントで打つことでミスが減る、高い打球点で打つことで威力が出る、などフットワークとドライブの質はリンクしています。
もうなんの練習をすれば良いか分からない!って人は取り合えずフットワーク練習をしておけばOK
自分にあった用具を使っていない
卓球が上達しない理由のひとつに誤った用具選びがあります。
多くの人は有名選手が使っているから、という理由でなんとなく選んでしまいがち。
例えばバタフライのインナーラケット、アウターラケットなどをとりあえず使う人が大半です。
しかし、本来は自分の体格や得意なプレー、苦手なプレー、さらには「思い切りの良いタイプか、丁寧にプレーするタイプか」といった性格まで考慮する必要があります。
そこを無視すると、自分に合わない用具で苦しむことになり、成長を妨げてしまいます。
一番多い誤り:弾みすぎる用具
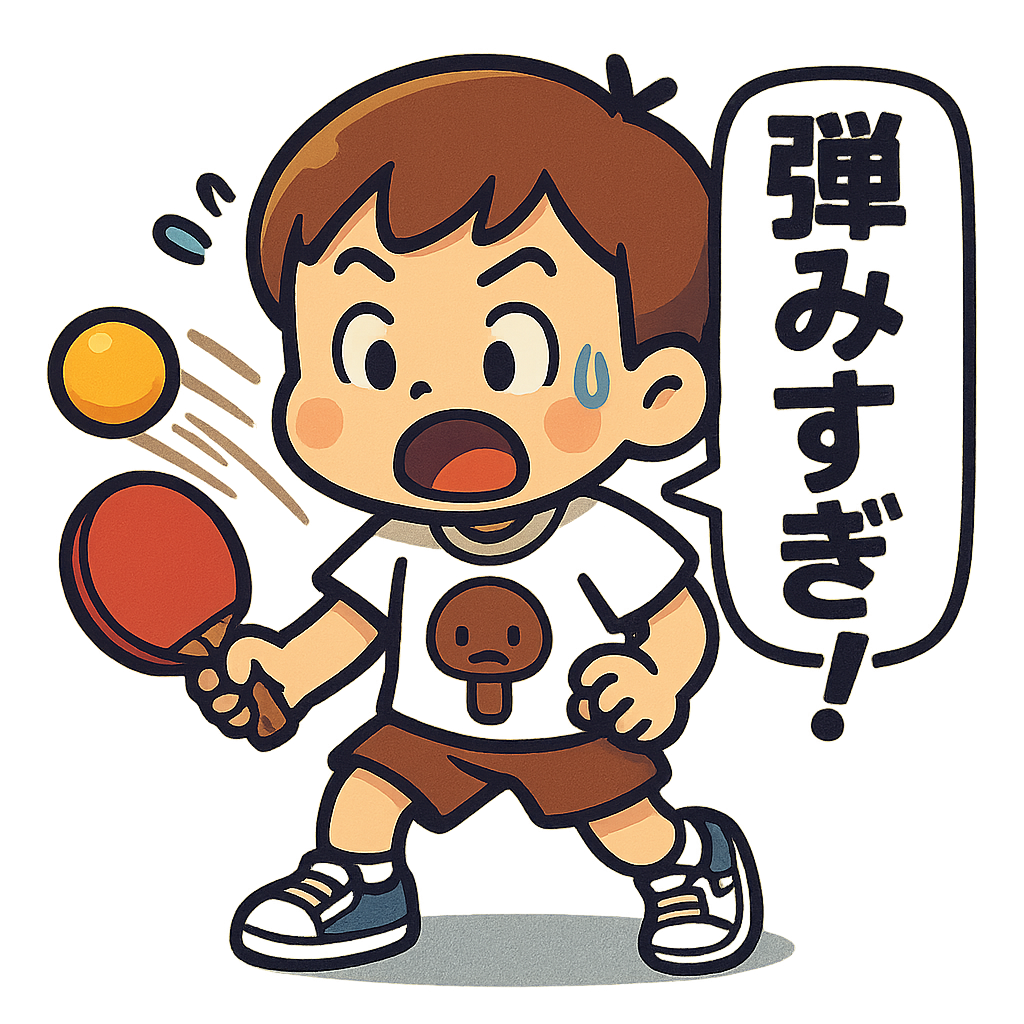
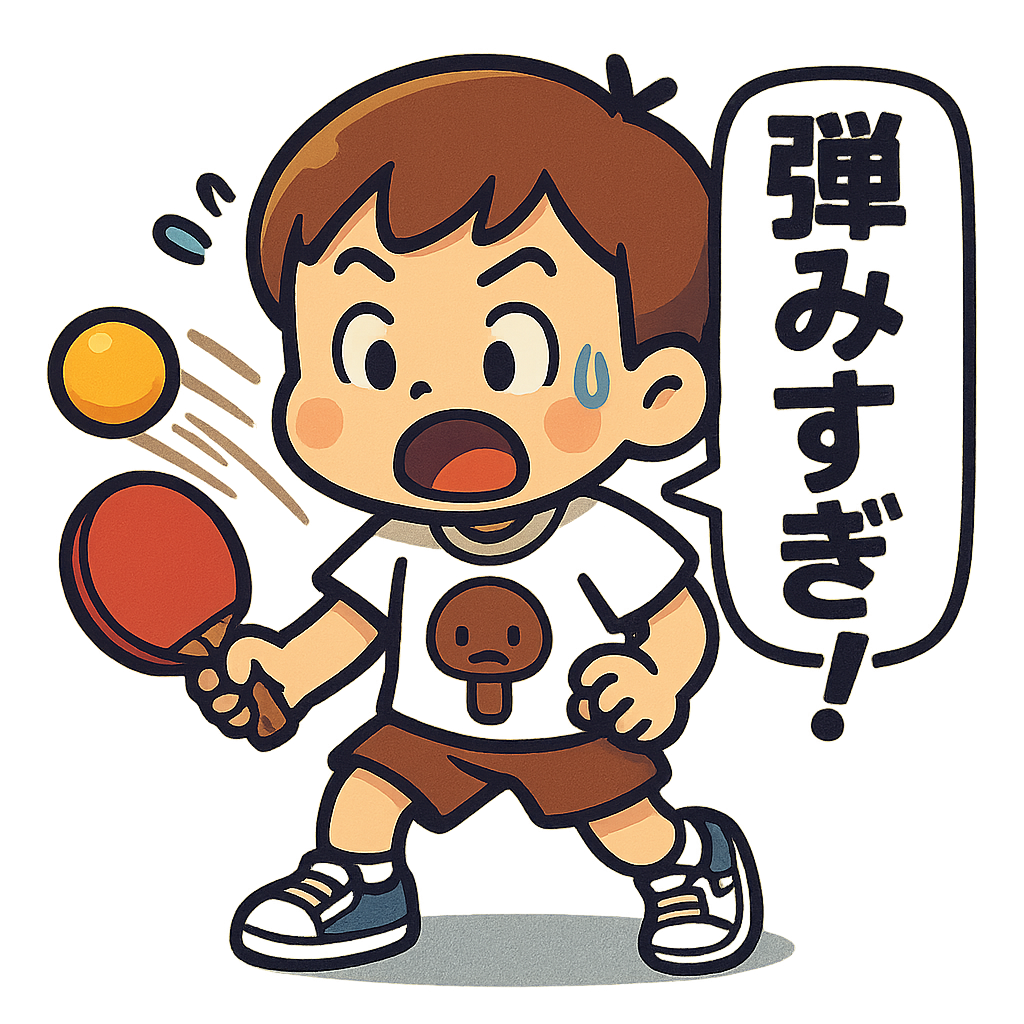
特にありがちな間違いが「弾みすぎるラケット」を選んでしまうことです。
ほぼ100%の卓球愛好家にとって、これはメリットよりもデメリットの方が圧倒的に大きいと言えます。
「攻めているときに威力のあるボールが打てる」という点は唯一のメリットですが、威力のあるボールなんてそこまで役に立ちません。
卓球は小学生やお年寄りが、高校生、大学生に普通に勝てるスポーツです。威力はそこそこでも十分得点になります。
弾む用具のデメリット
一方で、デメリットは数えきれないほどあります。
- サーブが長くなる
- ストップやツッツキが浮く
- ブロックやカウンターがオーバーする
つまり卓球で一番大事なコントロールが効かないという状況に直結します。
加えて、弾むラケットはカーボン入りのものが多く、ラバーも硬く重いため、操作性が悪化します。これがさらなるミスや安定感の欠如を生むのです。
重量の問題


弾むラケットは総じて重量が重い傾向にあります。これも上達を妨げる要因です。
重いラケットはスイングスピードを落とし、思った通りに振り切れなくなります。結果、唯一のメリットだった「威力のあるボールを打てる」という点すら活かせず、デメリットだけが残ります。
また、操作性の悪化によってラケット角度が出せず、振り遅れや取りこぼしも増えます。さらに、疲労も溜まりやすく、試合後半でパフォーマンスが落ちるリスクが高まります。
自分にあった用具を選ぼう
結論として、多くの人にとって「最新の弾むラケット」は無用の長物になりがちです。
自分の体格、プレーや性格を見直して、自分にあった用具を見つけましょう。
もしラケット選びに迷ったら、スワット(VICTAS)はおすすめ!
程よい弾みで、カーボンラケットのように勝手に弾んでいかず、しっかりコントロールできます。


才能がない
才能が無かったらいくら練習しても上手くなれません。
「才能がない」という言葉は、なんとなく口にしてはいけない雰囲気があります。
しかし、自分に才能があるのかないのかを冷静に自覚しておくことは大切です。
もちろん「才能がないから卓球をやるな」という話ではありません。そんなことを言えば、世界チャンピオン以外は卓球をする意味がなくなってしまいます。
重要なのは、才能があるかどうかを見極めたうえで「昨日の自分より今日の自分を強くするにはどうすればいいか」を考え続けることです。そうしたマインドを持つことで、楽しみながら上達を目指せます。
それに、卓球は総合的な競技
技術・戦術・フィジカル・メンタルなど多くの要素が複雑に絡み合っています。プロになるのであればすべてを高いレベルで備える必要がありますが、普通の選手であれば何か一つの武器があれば十分に戦えます。
隠れた才能に目を向ける
「才能がない」と感じても、それは卓球全般に当てはまるわけではありません。
例えば、ドライブの才能はなくてもブロックの才能があるかもしれない。ボールに強い回転をかけるのが苦手でも、相手の心理を読むのが得意かもしれません。
それはたくさん試合に出ないとわかりません。
たくさん試合をしていく中で、自分に何ができて、何ができないかが少しずつ分かってきます。
周りの人にアドバイスを求めるのも良いでしょう。
そうして経験を積んでいくことで自分の才能に気づけると思います。
練習量が足りてない
ここまでいろいろな要因を見てきましたが、シンプルに練習量が足りないから上手くなってないケースも多いです。
自分が思っているより、自分は練習していないし、周りの人は練習していたりするものです。
多くの人が「自分は上手くなっていない」と感じるのは、身近に比較対象がいるからです。
見えない練習時間の差
ただし、相手がどれくらい練習しているかは一概には分かりません。
部活動の練習時間だけが練習ではないからです。
- 家に卓球台を置いてサーブ練習をしている
- ランニングや筋トレなど体作りを継続している
- 授業中の休み時間にイメージトレーニングをしている
- ボール拾いのときに先輩の技術を観察している
- 練習メニューを自分で考えている
- 試合の合間にうまい人のプレーを観察している
- 自分が負けた試合を審判しながら「なぜ負けたか」を考えている
こうした時間もすべて「練習」です。
目に見える練習だけを比べて「自分の方が練習しているのに伸びない」と思ってしまうのは危険です。
まとめ
卓球が上達しない主な原因は、次の5つに集約されます。
- 無駄な練習をしている
- 必要な練習をしていない
- 練習量が足りていない
- 用具や戦型が自分に合っていない
- 才能がない
これらを一つずつ見直すことが、上達への第一歩です。





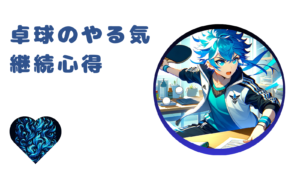
コメント